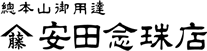
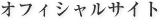

数珠の安田念珠店オフィシャルサイト TOP > 十代目社長のコラム > 第11回 ロビンソン・クルーソーの冒険(神との対話)2

そんな私達は、太平洋戦争の敗戦でそれまでとは180°変わった戦後教育を受け成長しました。それは、ルネッサンス以来西洋を世界の覇者とした、科学的合理主義思想を根底においた教育でありました。その教育の中で私達は、外界の一切を数量的に規定できるたんなる物質とみなす、17世紀のフランスの哲学者デカルトから始まる「機械論的世界観(自然観)」を植えつけられました。
私の家は、京都の古い商家です。そんな教育を受けた安田少年が家に帰ると、仏壇の中には仏様がおられ、先代のおじいさん、おばあさんの写真が飾ってあります。また、神棚や「おくどさん」や、家中のあちこちに神様が祀られているのです。事ある毎にその仏様や神様に手を合わせ拝むよう親から教えられたものです。要するに、お前は死んだら塵芥(ちりあくた)となって霧散するのだと教えられていながら、家の中には霊が溢れている。そして、そんな中で矛盾は少し感じながらも悩まずに成長してきたわけです。「機械論的世界観」では神や仏や霊といった物質として捉えることの出来ないものの存在を認めないわけですから、安田少年は自己の内面から外界を眺める基準として相反する二つのものを持っていたわけです。学問は論理的な矛盾を抱えては成り立たないですが、人生は成り立つということでしょうか。それとも、私は普通でない特殊な人間なのでしょうか。
前回のコラム「ロビンソン・クルーソーの冒険(神との対話)1」で長々と引用した「ロビンソン・クルーソー」の物語の中に、私は宗教というものの原点を見る思いがするのです。今回は神との対話という視点からみていきたいと思います。
物語は続きます。主人公ロビンソンはその後病気に罹ります。瘧(おこり)という表現が文章の中に出てきますから、多分マナリアに罹ったのでしょう。( 『おこり【瘧】間欠熱の一。 隔日または毎日一定時間に発熱する病で、多くはマナリアを指す。』 (広辞苑))
「6月18日。― 終日、雨。家の内に蟄居(ちっきょ)。雨がなんとなく冷たいような感じがした。それに少し悪寒がした。・・・・・・・・6月19日。― 体の具合がひどく悪い。悪寒をおぼえる。・・・・・・・6月20日。― ひと晩じゅうまんじりともしない。激しい頭痛、熱っぽい。6月21日。― 容態がひどく悪い。病気にはなる、看病してくれる者はいない、といったこの哀れな始末、こんなことを考えていると死ぬのではないかと不安になってくる。ハル沖で嵐にあって以来、初めて神に祈った。ただし、なんといって祈ったか、またなぜ祈ったか、ほとんどおぼえていない。頭がまったく混乱していたのだ。・・・・・・・」
(デフォー作 平井正穂訳 岩波書店 1967年 ロビンソン・クルーソー 上 120頁)
その後、病状は一進一退を繰り返しながらロビンソンの体力は日増しに衰えていきます。そして、その恐怖と絶望の境遇の中で、彼は神との対話を繰り返していきます。
「『主よ、私はなんというみじめな人間でしょう。病気になれば看病してくれる者もなく、ただ死んでゆくよりほかありません。いったい私はどうなるのでしょうか。』 涙がとめどなくあふれてきて、しばらくは口もきけなかった。」
(デフォー 平井 前掲書 125頁)
「私は思わず声をあげていった。『父の予言がついにあたったのだ。神の裁きがくだったのだ。みろ、私を助けてくれる者も話をきいてくれる者も一人もいないではないか。恵み深い神のおかげで私は幸福に安らかに生きてゆける身分に生まれついたはずではなかったか。それなのに、私はその神の思召しを聞こうとはしなかったのだ。私はそういう生活を自ら知ろうともしなかったし、またその祝福をいくら両親がいってきかせても聞こうとはしなかった。私の愚かさを悲しむ両親を私は少しも意に介さなかった。その報いで、私は今誰からもみすてられてただもう悲しみのどん底にいるのだ。・・・・・・・・・ところで今の自分はどうなのか。ほとんど人間の肉体では堪えられないような苦境にあえいでいるではないか。しかも助けも、慰めも、助言もないままに。』それから私は叫んだ。『主よ、私を助けて下さい。はげしい苦しみにさいなまれている私を助けて下さい。』 これがもし祈りといえるものなら、これこそ、永年の生涯を通じて私が神にささげた最初の祈りであった。」
(デフォー 平井 前掲書 上 126頁)
彼はこのようにして神との対話を次第に深めてゆきます。そしてその過程でブラジル人が病気の治療に煙草を用いていたということ思い出します。
「私がその箱の所へいったのは、疑いもなく神の導きによるものであった。箱の中に魂と肉体の両方をなおしてくれる薬を発見したからである。箱をあけてみると、そこに欲しいと思った煙草がはいっていた。また同じくしまっていた数冊の本もはいっていた。私は前にもちょっと話したことのある、例の聖書を一冊取りだした。このときまで聖書なぞはのぞくひまもなければ、第一、そんな気にすらなったことはなかった。くどいようだが、私は聖書をとりだした。」
(デフォー 平井 前掲書 上 129頁)
そして、ロビンソンは煙草をラム酒に浸し、それを飲む治療をこころみます。それをこころみるあいだ聖書を読みはじめます。
それでもいいかげんに開いてみて、最初に私がぶつかった言葉は次のようであった。『なやみの日に我をよべ、我なんぢを援けん、而(しこう)してなんぢ我をあがむべし。』」
(デフォー 平井 前掲書上 130頁)
「しかし横になる前に、私はそれまでの生涯を通じ、いまだかってやったこともないことをやった。つまり、私はひざまずいて、なやみの日に我をよべ、さらば我なんじを援けん、との約束を守りたまえと神に祈ったのだ。とぎれがちな、ふつつかな祈りではあったが、それがすむと煙草を浸したラム酒を飲んだ。」
(デフォー 平井 前掲書 上 131頁)
「7月3日。- 発作もついにさった。もっとも、体力が完全に回復したのは数週間後であった。体力が少しずつ回復にむかっているあいだも、私の頭には『我なんぢを援けん』という聖書の一句がこびりついて離れなかった。」
(デフォー 平井 前掲書 上 132頁)
二週間に亘るロビンソンの闘病生活も終わりを告げます。このあいだに彼の心の中で神の存在は大きくなり続けました。
「生活そのもののみじめさは相も変わらずであったが、私はようやく自分の境遇を前よりずっと楽な気持で眺めることができるようになっていた。たえず聖書を読み、神に祈ることによって、私の心はより高い世界にひかれるようになり、それまで少しも知らなかった内なる喜びをあふれるばかり味わうことができるようになった。」
(デフォー 平井 前掲書 上 134頁)
上の物語はロビンソン・クルーソーが、絶望的な境遇の中で病気に打ち勝つ様を描いています。彼は、なぜ病気に打ち勝つことが出来たのか。現代の常識では考えられないことですが、彼は煙草の葉を薬として使っています。もし、彼がふと思い出したブラジル人の薬(煙草)が病気に何らかの薬草的な治療効果を上げたなら、そして彼の強靭な体力もあわせて病気に打ち勝ったなら、上の物語は病気の治療過程を描いたものでしかないでしょう。ここで、我々の興味をひくのは、絶望的な境遇の中で彼は神と出会い、そして対話を深めていきながら絶望を乗り越え病気に打ち勝つ姿です。人間というのは弱い存在です。一人では何も出来ない。だから社会を作り協力し合って生きている。その存在が、たった一人で絶海の孤島へ追いやられる。それだけでも生きてゆくのは難しいと思われるのに、自分という存在をこの世から消し去ろうとする病魔が襲い掛かってくる。こんな極限の境遇の中でその魂の支えに神という存在にひたすら縋る。多分、自分がロビンソンであってもそうだったろうと、彼の姿に共感を覚える。それが、この物語の興味を惹く点だろうと思います。人間と宗教の出会いは、こんなものではなかったのかとも思えます。
冒頭に述べたように「機械論的世界観」でこの世界を眺めて見ると、この世に神が存在するとは決して思えません。しかし、与えられた世界観がどうであろうと、文明の力をすべて取り去って人間が生きていくという原次元においては、魂の救いとなるこの物語でいう神のような存在は必要であるということは理解できるのではないでしょうか。もし、人間が神という存在を伴わなかったら、今ここに存在していただろうかと、私は「ロビンソン・クルーソー」のこの一節を読みながら考えてしまうのです。
Copyright(c)1999-2016 YASUDA-Nenju Co,.Ltd All Rights Reserved.